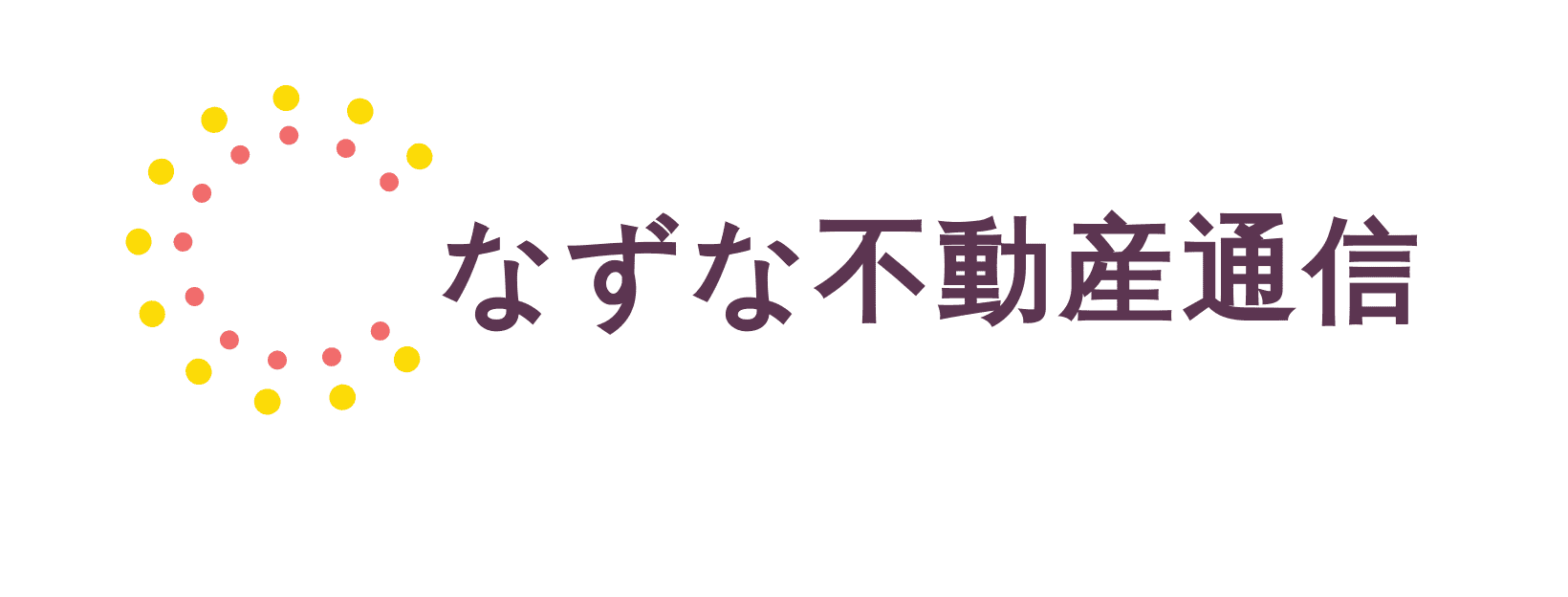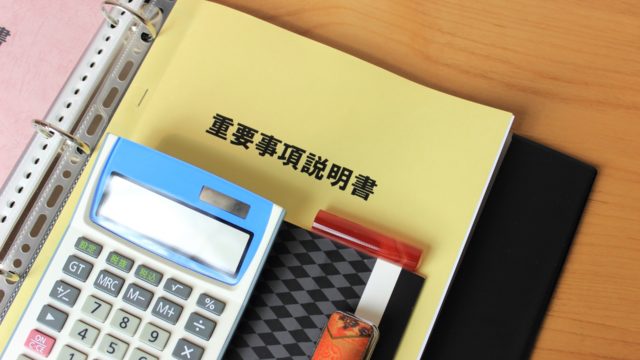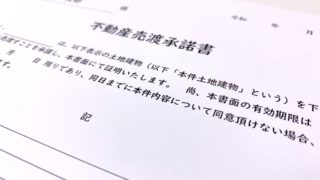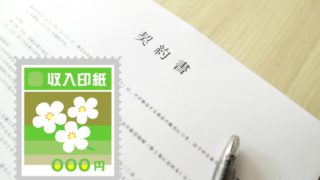マイホーム取得に伴い、考えておくべき資金計画!住宅ローンの知識や購入時にかかる諸費用など詳しく解説
今回の記事では、マイホームを取得する時に、事前に考えておくべき資金計画について詳しく解説できればと思っています。住宅購入にあたり必要になる金額や、住宅ローンの知識などを学んで、余裕をもった資金計画を立ててくださいね!
具体的に1つずつ見ていこうと思います。
購入者が調達できる資金
購入者が調達できる資金
調達できるお金 = 自己資金 + 住宅ローン + その他資金(親からの援助など)
住宅購入に必要な資金
必要な資金 = 住宅購入代金 + 諸費用
購入にかかる主な諸経費
以下に「○○の時」とありますが、その都度お金を用意するのか、もしくは最終的に住宅ローンの融資が実行された時に一括で払う場合などもあります。事前に不動産会社や建築会社にご相談ください。
売買契約の時
| 仲介手数料 | 成約価格×3%+6万円+消費税(残代金決済時で可の場合も) |
| 収入印紙 | 売買価格により税額が確定(→国税庁WEBサイト) |
金銭消費貸借契約(住宅ローン契約時)
| 融資事務手数料 | 3~5万円+消費税、もしくは融資額の1~2%前後+消費税(金融機関による) |
| 収入印紙 | 融資額及び特約により税額が確定 |
| 保証料 | 融資額の2%前後。(金利に上乗せで0円の場合も) |
●残金決済時・所有権移転登記時
| 所有権移転登記費用 | 司法書士の見積もりによる |
| 抵当権設定登記費用 | 司法書士の見積もりによる |
| 火災保険料 | 損害保険代理店の見積もりによる(約30〜50万円くらい) |
| 固定資産税・都市計画税精算 | 引き渡し日〜12月31日までの日割り精算 |
| 管理費・修繕積立金の精算 | 引き渡し日〜月末までの日割り精算 |
| 引越し費用 | 引越し業者見積もりによる |
| その他 | 不動産取得税、リフォーム費用、電気水道ガス工事、家具購入費等 |
購入代金の他に多くの諸費用がかかります。諸費用には、仲介手数料、ローンの諸費用、不動産取得税等の購入代金以外にかかる費用が多数あります。
諸費用のおおよその目安は、購入状況によっても異なるのですが、一般的に購入代金の1割前後が目安とされています。中古住宅を購入してリフォームを予定しているときは、リフォーム費用も別途必要になります。
また、新築の場合には追加工事のお金がかかるケースもあります。
例えば、カーテン、エアコン、証明、表札など、実際に住むには別途費用がかかることもあります。
住宅ローンの基礎知識
マイホームを購入する際は長期のローンを組んで、毎月にわたって返済していくのが一般的です。資金計画を立てる上で融資可能な金額を目安として把握しておくことは重要です。
金利の怖い1%の差
住宅ローンは大きなお金を長期にわたって借り入れるため、金利がたった1%違うだけで、数百万円支払額が変わってくることもあります。また、変動金利の場合、金利は安いですが金利変動によって毎月の返済額が異常に高くなって支払えなくなるというケースもあります。
変動金利の場合、金利が低く毎月の返済額が低いうちに余裕を持って貯金し、繰上返済などで金利変動に対応していくのが良いと思います。
固定金利と変動金利
全期間固定金利型(金利の変動がない)
借り入れた当初の金利が全期間変わりません。
| メリット | 市場の金利に変動があっても、全期間支払額が一定なので安心。そして資金計画などが立てやすい。 |
| デメリット | 変動金利型などに比べて金利が高い。 |
変動金利型(金利の変動がある)
返済期間中、定期的に金利が見直されます。
| メリット | 固定金利型に比べて金利が安い。 |
| デメリット | 金利の変動がある。金利は半年毎で、返済額は5年毎に見直しがあります。 |
固定金利期間選択型(金利の変動がある)
借り入れた当初の金利が一定期間は変わりません。
| メリット | 全期間固定金利よりは金利が安く、一定の期間は金利変動がなく安心。 |
| デメリット | 金利の変動がある。一定の期間終了後、金利が上がる可能性があります。 |
フラット35
住宅ローンには、民間金融機関の一般的な住宅ローンと、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携した「フラット35」があります。
詳しくは住宅金融支援機構のWEBサイトへ
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/flat35.html
フラット35は、全期間固定金利型住宅ローンで、変動金利に左右されることはなく返済額が一定のため安心です。ですが、融資対象の住宅には一定の条件がありますので、全ての住宅で融資が受けられるとは限りません。
こんな方に向いているフラット35
- 安定した資金計画を立てたい方
- 金利上昇リスクが怖い方
- 質の高い住宅を取得する方
- 計画的に繰上げ返済したい方
ずっと固定金利で安心
資金の受取時に、返済終了までの借入金利と返済額が確定します。
多彩なメニューで安心の住まいづくりを応援
質の高い住宅の取得を支援する【フラット35】Sなどがあり、また、住宅金融支援機構が定める技術基準に基づく物件検査を実施します。
保証人不要、繰上返済手数料不要
保証人は必要ありません。
返済中に繰上返済や返済方法の変更を行う場合の手数料もかかりません。
ご返済中も安心サポート
万一のことがあった場合に備えて、新機構団信や新3大疾病付機構団信などがあります。また、多様な返済方法変更のメニューをそろえ、ご返済のお悩みに対して、事情に合った返済方法をご提案してくれます。
住宅ローン融資の審査
住宅ローンの審査は、基本的に収入の有無や安定性の他に、勤続年数、現在の借入額(車やクレジットカード)、過去の借入額の遅延延滞状況(引き落としができなかったなど)、健康状態などが重視されます。
過去に返済が滞った事がある場合では、延滞の発生時期と期間がポイントになります。
勤続年数や勤務先
勤続年数は金融機関によっても異なりますが、1年〜3年の勤続年数が必要となってきます。長い勤務年数ほど有利になります。場合によっては契約社員や派遣社員は対象外になることもありますので、金融機関にご確認ください。
完済時の年齢
金融機関によっては40年ローンなどの商品があったりしますが、その場合でも例えば、完済時の年齢が75歳までといった条件があったりします。住宅ローン商品の完済時の年齢もチェックしましょう。
個人信用情報
クレジットカードや、銀行の引き落としなどで過去に延滞があった場合、借入が難しくなることもあります。その場合でも、かなり昔だった場合には大丈夫なケースもあります。
年収
住宅ローンにおいて計算するときは、手取り額ではなく税引前年収で計算します。
自己資金
マイホームを取得しようと思った時に、どのくらいの自己資金が必要となってくるのでしょうか。
近年では、頭金なし、自己資金なしでも住宅を買うことは可能ですが、自己資金として1〜2割ほど用意しておくと、金利の優遇があるケースなどもあります。前述したように、金利の差が総支払額に大きな影響を受けますので、自己資金をなるべく用意しておいた方が良いです。
また、細かいお金もちょこちょこ必要になってきます。例えば、手付金、カーテン代、エアコン代金など。
マイホームを取得しようと思った時には、あらかじめ自己資金の準備をお勧めします。
余裕を持った資金計画をしましょう
資金計画は、自己資金+住宅ローンなどの借り入れ金が一般的ですが、これらの他に、親からの資金援助などが考えられます。
住宅ローンに関して、低金利時代が続いていますので、低金利で多くの融資を受けることができますが、無理をして上限ギリギリに近い融資を受けると、ローン破綻を招く危険性が高くなります。将来、子供が増える可能性もあるため、教育資金のことも考えておかなければなりません。
現時点での安定した収入を基準に、余裕のある返済額の範囲で借入額を決めることが大切です。
「どれだけ借りられるのか?」ではなく「毎月いくらなら返済できるのか?」を考えていく方が圧倒的に大事です。
マンション購入の場合は、毎月の借入金の返済額だけでなく、管理費・修繕積立金等が毎月必要になりますので、その費用も考えておく必要があります。
以上の話しを踏まえても、よく分からなかったという方は、不動産会社、または建築会社に相談すればより具体的に教えてくれます。また、住宅ローンに関して言えば、金融機関に相談するのも良いと思います。
ぜひ、ご参考にしてください。
住宅ローンに関しておすすめBOOK
 | 住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本 [ 千日太郎 ] 価格:1,650円 |